院長社本の健康コラム
歯やお口に関するケア、トラブル解決法をご紹介します。
梅雨の気象病って?
6月に入り、梅雨入りの知らせがあちこちから聞こえて来ます。
梅雨は農耕民族である日本人にとって、恵みの雨でした。
とはいえ、梅雨が鬱陶しいのも事実です。
また、梅雨の時期に出る“気象病”という症状が、最近注目されています。
◆気象病とは
梅雨時、鬱々と気が滅入るだけでなく、冷えや肩こり、頭痛や関節の痛みなどに苦しんでいる人がいます。
これらの症状が出たら、「気象病」の可能性があります。
気象病は、気象の変化によって身体にさまざまな症状が出たり、既往病が悪化したりするものです。
急な気圧の変化や気温、湿度の変化に身体が慣れておらず、うまく対応できないことから発症します。

◆気象病の症状は?
<冷え、肩こり、腰痛>
梅雨の時期は気圧・気温・湿度が刻一刻と変わるため、真冬よりこの時期に「冷え」「肩こり」「腰痛」を感じる人が多いといいます。
気温は夏へと向かって上昇し、電車や公共施設、商業施設などは冷房を使いはじめます。
しかし、梅雨の時期は寒暖差が激しく、身体が慣れておらず温度調整がしにくいことから冷えや肩こり、腰痛などが出てしまいます。

<頭痛・ぜんそく・古傷の痛み>
「雨が降る前は頭が痛くなる」
「梅雨時は昔の傷が痛む」
「台風が来るとぜんそくが出る」
というように、気圧は身体の調子と大きく関係しています。
気圧が変化すると、人間の体はストレスを感じ、それに抵抗するために自律神経が活性化します。
自律神経系には交感神経と副交感神経があり、交感神経は血管を収縮させて心拍数を上げて身体を興奮させ、副交感神経は血管を広げて身体をリラックスさせます。
急激な気圧の変化で、この交感神経と副交感神経の調整がうまくいかなくなると、気象病として身体の不調を引き起こしてしまいます。
◆ 気象病の対策は?
・お天気と体調の関連性を日記につける
・規則正しい生活を心がける
・夏日でも羽織るものを用意する
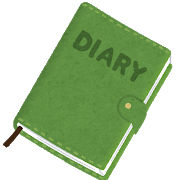
日常でこのような対策をすることはもちろんですが、症状がひどいようであれば、専門医に相談したほうが良いでしょう。

 健康コラム一覧に戻る
健康コラム一覧に戻る