院長社本の健康コラム
歯やお口に関するケア、トラブル解決法をご紹介します。
おせち料理を楽しもう!
日本人にとって、お正月の食卓といえば「おせち料理」ですよね。
おせち料理は、「祝い肴」「口取り」「焼き物」「酢の物」「煮物」の5種類からできていて、実は懐石料理と同じようにコース料理になっています。

また、おせち料理は重箱に詰めるのが一般的ですが、実はこの重箱にも「幸せを重ねる」という意味が込められています。
デパートなどで市販されているおせち料理は、2段・3段が主流ですし、中には5段のおせちもあるようですが、正式な段数は4段なのだそうです。
完全な数を意味する「3」にもう一段重ねるという意味で4段なのだそうですが、この4段の重にも一段一段に意味があり、詰める食べ物も決まっています。
一の重・・・「祝い肴」「口取り」
二の重・・・「焼き物」
三の重・・・「酢の物」
与の重・・・「煮物」
ちなみに、数字の四は死を連想させて縁起が良くないということで、「与の重」の文字があてられています。
3段重の場合には、一の重に「祝い肴」と「口取り」、二の重に「焼き物」と「酢の物」、三の重に「煮物」を詰めます。

2段重の場合には、一の重に「祝い肴」と「口取り」、二の重に「煮物」を詰め、残りは好みで振り分けます。
実は、おせち料理にもこのようなしきたりがあります。
また、料理ひとつひとつにおめでたい意味やいわれがあり、地域によって多少の違いはありますが、すべてそろえると20~30種類にもなります。
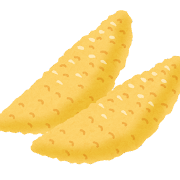
その中でも代表的なものを「祝い肴三種」といい、この三品と餅が揃えばおせちの形式が整い、お正月が迎えられるとされています。
しかも、その三品は関東と関西で異なります。
関東では黒豆・数の子・田作り、関西では黒豆・数の子・たたきごぼう、これが「祝い肴三種」です。
おせちをつくるとき、買うときには、この3種類は揃うようにしたいですね!
◆ おせちづくりにチャレンジ!祝い肴三種のレシピ





 健康コラム一覧に戻る
健康コラム一覧に戻る