院長社本の健康コラム
歯やお口に関するケア、トラブル解決法をご紹介します。
ひみこのはがいーぜ!
「ひみこの歯がいーぜ」この標語ご存知ですか?
弥生時代の人々は、1回の食事に約4000回も噛んでいたと言われることから、しっかり噛むメリットを知ってもらうために作られた標語です。

よく噛むことは、単に食べ物を体に取り入れるためだけではなく、全身を活性化させるためにとても重要な働きをしています。
◆ ひ:肥満予防
よく噛んで食べると脳にある満腹中枢が働いて食べすぎを防げます。
よく噛まずに早く食べると、満腹中枢が働く前に必要以上に食べ過ぎてしまい、その結果太ってしまいます。
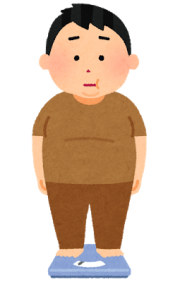
◆ み:味覚の発達
よく噛んで味わうことにより、食べ物の味がよくわかります。
味覚は年齢に応じて少しずつ発達していきます。生命維持のための炭水化物の必要性という生理的欲求から、幼い頃は甘いものを好みます。
幼い頃は「酸味」や「苦味」を理解するのは難しいですが、身体の発育とともに味覚も発達していき、食べられるものが増えていきます。
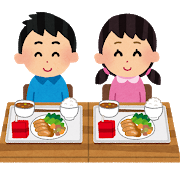
さまざまなものを食べることによって、経験や学習が積まれ慣れていくものです。
偏りなく食べる機会を作り、よく噛んで肥満を防止し、味覚を発達させましょう!
◆ こ:言葉の発音がはっきり
よく噛むことにより口の周りの筋肉を使うため、表情が豊かになり、子どもは永久歯が生える十分なスペースを確保できるようになります。
その結果、言葉の発音がはっきりとできるようになったり、表情も豊かになって笑顔がぐっと素敵になったりします。

また顎の骨の成長を促すことで、顎の大きさと舌の大きさとのバランスが良くなり、十分に舌を動かすスペースができ、滑舌が良くなります。
◆ の:脳の発達
よく噛む運動が脳細胞の働きを活発にすることで、脳が活性化するので、子どもの知育を助け、高齢者は認知症の予防に役立ちます。
「噛む」という動作によって、歯の根っこの表面(歯根膜)や顎を動かす筋肉にあるセンサーが脳へ運動刺激を伝えます。
この運動刺激は、歯や顎の位置が脳に近いために非常に強く、脳が受ける1日の運動刺激のうちの約50%を占めるほどと言われています。

噛むことを意識し、家族と楽しい雰囲気で食事をすることで脳を活性化しますので、よく噛んで食べる習慣をもう一度見直してみましょう!
残りの「歯がいーぜ」については、また次の機会にお話ししたいと思います。

 健康コラム一覧に戻る
健康コラム一覧に戻る